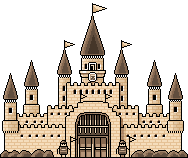<ぶらり京都>
<お座敷遊び>
「和」の趣が残る街並みが美しい都市・京都。
その京都の街を一層、華やかにする存在・「舞妓さん」。
舞妓さんに接することができる「お座敷遊び」は、一生に一度は楽しみたいものですよね。
舞妓さんは、芸妓さんになる前の見習い期間の少女のこと。
年齢は15歳から20歳くらいで、可愛らしく華やかな着物にだらりの帯、かんざしなどが特徴。
舞妓としての見習いが終わり、卒業すると襟かえという儀式をして芸妓さんになります。
芸妓さんには舞を担当する“立ち方さん”と三味線・歌を担当する“地方さん”がいて、
舞妓さんと三人で宴席を盛り上げてくれます。
   
<一見さんお断り>
一つひとつの“ご縁”を命のように大切にするお茶屋さん
花街では、信頼のおけるお客さんからまた別のお客さん…と、
“人伝い”のつながりによって人の輪を広げていくのが流儀なのです。
一方、長年ご贔屓のお客さんにとって、お茶屋という空間は、 “我が家”のようなもの・・・
このプライベートな場に、
「面識のまったくないお客さん=一見さん」を入れ、酒宴をひらくということは、
見ず知らずの通行人をいきなり自宅に招き入れて食事を共にすることと同じです。
「一見さんお断り」といわれると、突っぱねられたような気分になりますが、
その言葉の裏には、商いを営む側として、
自ら危険を招き入れるような真似は最初からしない、ということが第一にあるのです。
お茶屋さん、女将さんとの間に結ばれた固い絆=『家族』のような信頼関係があるからですね。
 
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

国際交流会館 |
Restaurant TSUMUGI
〜古都の景色につつまれて〜
古都の絶景と庭園。季節を五感で感じる旬の料理
「季節を食べる」がコンセプトの京フレンチです。
 |

蛤御門 |
京都御苑の西側、もとは新在家御門といい、
閉じていたが天明の大火(1788)の際、
開門、‘焼けて口あく蛤’にたとえて
蛤御門とよばれる。
 |

椋(むく)の巨木 |
この大きな椋の木は、
このあたりが清水谷という公家の屋敷
であったことから「清水谷家の椋」と呼ばれています。
樹令は約300年くらいで
御苑内でも数少ない椋の大木です。
1864年の蛤御門の変の時、
長州藩士、来島又兵衛がこの木の付近で
討死したとも伝えられています。 |